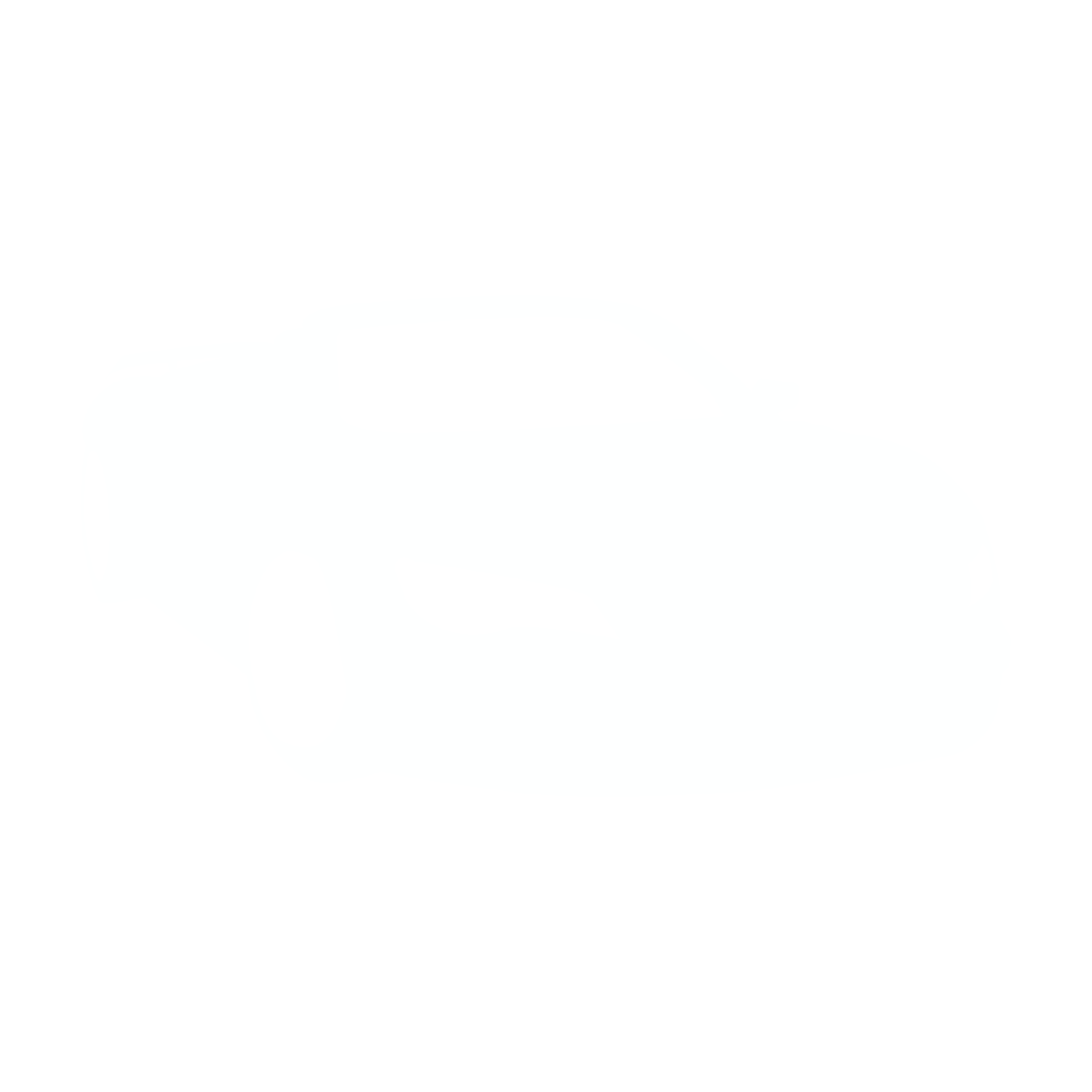前回のページでは、高次脳機能障害として認定されるには、脳外傷を原因とする障害であることが条件になると記載しました。
脳外傷がない場合は、非器質的精神障害として、高次脳機能障害とは別に扱われます。
今回は、高次脳機能障害として等級認定されるための条件について、記載していきます。
高次脳機能障害として、自賠責保険の後遺障害等級における第一級~第九級のどの等級に認定されるかは、以下の内容で検討されます。
①脳外傷を原因とする障害であるか
②障害の内容と程度
今回のページでは、上記の①について記載していきます。
①脳外傷を原因とする障害であるか
そもそも、脳外傷を原因とする障害でなければ高次脳機能障害とは認定されません。
脳外傷を原因とする障害であると言うには、
(1)脳外傷があること
(2)障害が高次脳機能障害の特徴的な障害であること
を満たす必要があります。(1)(2)それぞれのポイントは以下になります。
(1)脳外傷があること
(ⅰ)事故直後の意識障害の程度と時間:
事故後の意識障害が長いほど、組織が損傷している可能性が高いと判断されます。
・「昏睡~半昏睡で開眼・応答しない状態(JCSが3桁、GCSが12点以下)が少なくとも6時間以上継続した場合
・「健忘症あるいは軽度意識障害(JCSが2桁~1桁、GCSが13点~14点)が少なくとも1週間以上継続した場合
どちらかを満たした場合は、高次脳機能障害を残すことがあるとされています。
しかし、上記レベルの意識障害が高次脳機能障害として認定されるために必ずしも要求されているわけではなく、より軽度の意識障害しかなくても、高次脳機能障害として認定される可能性があります。
医師の診断書やカルテに意識レベルは記載されていますが、記載がなく、(ⅱ)(ⅲ)の条件も満たさないとなると、高次脳機能障害として認定される可能性は非常に低くなります。
※JCS(Japan Coma Scale):意識レベルの指標であり、脳血管障害や頭部外傷の急性期における意識レベルを評価することが可能です。
Ⅰ:刺激しないでも覚醒している状態(Ⅰ桁で表現)
・0:意識清明
・Ⅰ-1:だいたい清明であるが、今ひとつはっきりしない
・Ⅰ-2:見当識障害がある(時間や場所、日付が分からない)
・Ⅰ-3:自分の名前、生年月日が言えない
Ⅱ:刺激で覚醒するが、刺激をやめると眠り込む状態(Ⅱ桁で表現)
・Ⅱ-10:普通の呼びかけで容易に開眼する
・Ⅱ-20:大きな声または身体を揺さぶることにより開眼する
・Ⅱ-30:痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すことにより開眼する
Ⅲ:刺激しても覚醒しない状態(Ⅲ桁で表現)
・Ⅲ-100:痛み刺激に対し、払いのける動作をする
・Ⅲ-200:痛み刺激に対し、少し手足を動かしたり、顔をしかめたりする
・Ⅲ-300:痛み刺激に反応しない
※GCS(Glasgow Coma Scale):意識レベルを「開眼」4段階、「発語」5段階、「運動」6段階にそれぞれ分けて、各項目ごとの最良応答で評価、合計点で重症度(緊急度)を判断できます。点数は低ければ低いほど、緊急度が高いことになります。
E:eye opening(開眼)
・4点:自発的に開眼
・3点:呼びかけにより開眼
・2点:痛み刺激により開眼
・1点:痛み刺激でも開眼しない
V:best verbal response(最良言語機能)
・5点:見当識あり
・4点:混乱した会話
・3点:不適当な発語
・2点:理解不明の音声
・1点:発語なし
M:best motor response(最良運動反応)
・6点:命令に応じる
・5点:疼痛部位を認識する
・4点:痛み刺激から退避する
・3点:痛み刺激に対して屈曲運動を示す
・2点:痛み刺激に対して伸展運動を示す
・1点:痛み刺激に対して反応なし
(ⅱ)交通事故による頭部外傷の診断があること:
初診時に頭部外傷の診断があることです。
外傷性くも膜下出血や脳挫傷等の頭部外傷を示す診断名が記載されていることが重要です。
(ⅲ)脳損傷の画像所見があること:
脳の損傷が発生したことを証明する受傷後の画像+脳の損傷により生じた障害が残存したこと証明する画像があることが重要です。
それらの画像により、
a)脳内(皮質下白質、脳梁、基底核部、脳幹など)に点状出血しているか
(b)脳室拡大、脳萎縮があるか
(c)脳挫傷、頭蓋内血腫などがあるか
がポイントになります。
高次脳機能障害を認定するためには、CT・MRIなどの画像検査資料(特に頭部)が重要な判断資料となるので、自賠責からは、交通事故直後から症状固定までの画像検査資料の提出を求められます。
画像上明らかであれば良いですが、画像上明らかでない場合もあります。
例えば、脳挫傷であることが明確に確認できないが、広範囲で脳の神経細胞の繊維が断裂している場合は画像所見として確認できないことがあります。
もちろん、画像上明らかでない場合でも頭部外傷の診断名があれば、高次脳機能障害として認定される可能性はあります。
事故直後、意識レベルが低かった、強く頭部に衝撃が加わった等の事情があれば、念のため画像検査を受けておくほうが良いでしょう。
(a)脳内(皮質下白質、脳梁、基底核部、脳幹など)に点状出血していることを示す画像所見
脳内の点状出血痕、脳室内出血、くも膜下出血などは、びまん性軸索損傷を示唆するものです。
(b)脳室拡大、脳萎縮を示す画像所見
受傷直後から撮影された画像資料を時系列で比較すれば脳室拡大や脳萎縮の有無を確認できることがあります。
脳外傷後に脳の体積減少により脳室拡大や脳萎縮が進行することがあり、このような変化が生じる場合、ほぼ3ヶ月程度で変化は固定します。
自賠責の高次脳機能障害認定で脳室拡大・脳萎縮の画像所見は、脳損傷が推定されることになるため大変重視されています。
(c)脳挫傷、頭蓋内血腫などの局在性脳損傷を示す画像所見
高次脳機能障害は主として、びまん性脳損傷を原因として発症しますが、局在性脳損傷(脳挫傷、頭蓋内血腫等)との関わりも否定できず、また、両者が併存することもしばしば見られます。
そのため、局在性脳損傷の画像所見も重視されます。
(d)CT、MRI以外の画像所見
自賠責における後遺障害認定でも、裁判における認定でも、CT、MRIの画像所見がとくに重視されていますが、CT,MRI以外の画像所見としては以下のものが挙げられます。
・PET、SPECT
PET(ポジトロン・エミッション・トモグラフィー)は、陽電子放出アイソトープを体内へ注入すると、体内の陰電子と結合して消滅放射線を発生する性質を利用して、それを検出器で測定し、コンピュータで処理して断層画像化するものです。
SPECT(シングル・フォト・エミッションCT)は、体内に注入した放射性同位元素の分布状況を断層画面で見る検査です。
双方とも脳の断面の血流状態がよくわかり、血液が流れていない虚血領域を確認することができます。
しかし、いずれも脳の機能低下の確認はできても、必ずしも脳損傷の推定までされるものではありません。
スポンサーリンク
また、脳損傷によらない精神障害の場合にも、同じような画像所見が得られるとの見解もあるため、自賠責の高次脳機能障害認定では重視されず、裁判においても重視されないことが多いですが、いくつかの裁判では、このような機能的画像診断の結果を有用と判断した例もあります。
補助的な証拠としての価値が認められる可能性があるため、これらの画像診断を行う意味はあると思われます。
・拡散テンソル画像(DTI)
脳内の神経繊維に沿った水分子の拡散の動きを確認することで、脳内の神経繊維の状態を推定するためのものです。
しかし、微細な脳損傷の有無を判断することはできず、画像精度も不十分で、画像の解釈も確立しているとはいえないことから、現時点では、脳損傷を認定するための決定的な証拠にはなりません。
・fMRI(磁気共鳴機能画像法)
手や指を動かすといった課題に対して、脳の中枢が賦活化され、相対的にデオキシへモグラビン量が変動します。
その変動をMRIによって画像化することで脳の活動を確認できるのがfMRIですが、微細な脳機能の低下に対しては、あまり有用といえないのが現状です。
・MR(磁気共鳴)スペクトロスコピー
脳内にある分子の種類と量をグラフの高さにより表示するものですが、環境に影響されやすく、あまり有用とは言えません。
上記(ⅰ)~(ⅲ)の全てが揃っていれば高次脳機能障害として認定される可能性が非常に高まります。
どれか一つでも欠けていくと、その分認定されるのが難しくなっていき、(ⅰ)~(ⅲ)全て欠けていると認定される可能性が非常に低くなります。
(2)障害が高次脳機能障害の特徴的な障害であること
高次脳機能障害の特徴的な障害として、認知障害や行動障害、人格変化等が挙げられます。
認知障害や行動障害、人格変化の有無や内容、程度は
(ⅰ)日常生活の状況報告
(ⅱ)学校生活の状況報告
(ⅲ)神経心理学的検査
などから判断され、交通事故前後で、被害者の生活に具体的にどのような変化が生じているかを検査します。
(ⅰ)日常生活の状況報告:
家族、近親者や介護者など、被害者と日常生活で接している人が作成する報告書です。
自賠責保険には定型の書式が用意されています。
被害者の日常活動の能力、問題行動の有無、家庭・地域社会・職場・学校での適応状況、就労・就学状況、身の回りの動作能力などを記載します。
なお、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」(自賠責が用意する定型の書式)にも、身の回りの動作能力や、認知・情緒・行動障害の症状、家庭・地域社会・職場・学校での適応状況が記載されます。
(ⅱ)学校生活の状況報告:
交通事故前と事故後の学校の担任教師が作成する報告書です。
自賠責保険に定型の書式が用意されています。
被害者について、事故前と事故後の学習面、学校での過ごし方、精神・性格面などを記載します。
(ⅲ)神経心理学的検査:
脳の各機能を検査する方法は数多くありますが、その中のいくつかを記載していきます。
(a)脳の全般的機能の検査(知能テスト)
・WAIS-Ⅲ(ウェクスラー成人知能検査)
成人の全般的脳機能評価する為に最もよく利用される検査で、適用年齢は16歳~89歳です。
16歳以下の場合はWISC-Ⅲという知能検査があります。
言語性検査(VIQ):知識、数唱、単語、算数、理解、類似、語音整列の下位検査
動作性検査(PIQ):絵画検査、絵画配列、積木模様、組合わせ、符号、記号探しの下位検査
この両者の検査を総合して総合IQ(FIQ)を算出します。
平均得点は100点で、標準偏差は15点です。
すなわち、通常人の多く(約3分の2程度)は85点~115点の間に収まります。
所要時間は2時間程度の検査になります。
(b)認知機能に関する検査
・MMSE(mini-mental state examination)
認知機能を評価する簡易な検査方法です。
30点満点の11の質問で構成されており、見当識、記憶力、計算力、言語的能力、図形的能力をカバーしています。
24点以上で正常と判断され、20点未満は中程度の、10点未満は高度な知能低下と診断されます。
・長谷川式認知症スケール(HDS-R)
認知機能を評価する簡易な検査方法で、所要時間は10~15分程度です。
言語性知能検査のため、失語症や難聴があると検査が困難になります。
30点満点で、20点以下が認知症の可能性が高まるとされています。
認知用であることが確定している場合は、20点以上で軽度、11~19点の場合は中程度、10点以下は高度と判定されます。
(c)言語機能の検査
・標準失語症検査(SLTA)
日本で最もよく用いられている総合的な失語症検査です。
26項目の下位検査により構成され、聞く、話す、読む、書く、筆算の五つについて検査します。
検査の所要時間は60~120分程度、場合によっては120分以上の時間を要します。
・WAB失語症検査
38項目の下位検査により構成され、自発話、話し言葉の理解、復唱、呼称、読み、書字、行為、構成の八つを評価します。
失語指数(失語の重症度)が算出されるため、どれだけ良くなったもしくは悪くなったが判別しやすい検査です。
(d)遂行機能に関する検査(遂行機能障害は前頭葉の障害により生じます。)
・WCST(ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト)
最初に1組の反応カードが配られ、それらを色、形、数の3つの分類基準に基づいて並べ替えさせます。
所要時間は20分程度で、対象年齢は6歳半~89歳です。
(e)記憶に関する検査
・WMS-R(ウェクスラー記憶検査)
記憶の様々な側面を測定できる検査です。
13の下位検査で構成され、一般的記憶と注意・集中力の2つの主要な指標や、視覚性記憶と言語性記憶に分けての評価ができます。
また、遅延再生による評価も可能です。
100点を中心として標準偏差は15点です。
所要時間は45分~60分、対象年齢は16歳~74歳です。
・三宅式記銘力検査(東大脳研式記銘検査)
聴覚性言語の記憶検査です。
関連のある対語(例:病気-薬)10対と関連のない対語(例:正直-たたみ)10対を読んで聞かせた後に、片方を読んでもう一方を想起させます。
1回の得点を10点満点とし、同じことを3回繰り返します。
上記は例ですが、これらの神経心理学的検査により、ある程度は、認知障害や行動障害を評価することができます。
しかし、情動障害(人格変化)を評価することはできません。
自賠責が提出を求める「神経系統の障害に関する医学的意見」(自賠責が用意する定型の書式)に神経心理学的検査の所見が記載されます。
また、入院中等に付き添っていた家族等の方が被害者の行動や性格についてメモ等を残していれば、医師の書類と違って証拠資料とまではいきませんが、補助的な資料として参考にされることもあります。
大切なのは、認知や行動における障害と情動障害(人格変化)で、また被害者が抱えた障害の種類によって必要な検査や証拠となる資料が変わってくること。
また、一番大きな障害だけでなく、軽微であっても事故前から変化が生じている能力がある場合は、そちらも検査をしておくことです。
一番大きな障害だけでなく、その他の障害も合わせると実際に認定を受けられる等級が変わる可能性もあるためです。
スポンサーリンク